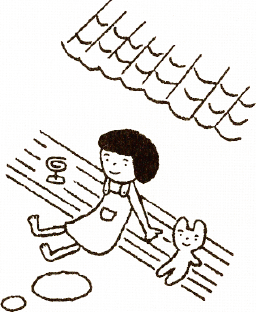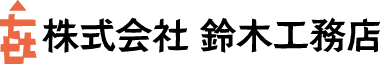先週末、麻生区で開催した建築中現場見学会のレポートをお届けします。
「建築中現場見学会」でわかること
仕上げ前の建物の状態を公開しているので、木の構造体や金物、断熱材や下地などを直接見て確かめることができます。基礎などすでに見えなくなっている部分や、屋根などについては、工事中写真をスライドにまとめて現場監督が解説します。

立上部に打継のない「一体打ち」による基礎。周縁部で構造を受けて、中心部は極力基礎の壁を立てない構造。円形の束柱は、床下暖房の気流を妨げない工夫
たとえば、鈴木工務店の現場は、基礎にも特徴があります。「基礎一体打ち」を採用していて、底部と立上部を打継なく一体でコンクリート打ちをします。打継が生じないことで隙間が出来ず、床下の気密性が保たれます。床下暖房(エアコンの暖気を床下に送り込んでコンクリートに蓄熱、床の吹出口から暖気を室内へ届ける)を行う上で大事な工程となります。隙間が生じないことで、シロアリの侵入も防ぐことができます。職人さんにとって一体打ちはちょっとした手間なので、誰でもやってくれるわけではありませんが、パートナーの基礎屋さんは、一体打ちの意味を理解しているプロ。継ぎ目のない美しい基礎を打ってくれます。
現場の安全や整理整頓の状態をチェック

コンパクトな住まいでも、整理整頓で極力床に物が置かれない状況を保ちます。現場照明や電気工具類のコードも上から吊ると引っ掛かりもなく安全性も高まります。
現場にゴミが山積みだったり、資材や道具類で足の踏み場がなかったり、コード類が床を這っていたり。乱雑で安全に配慮が足りていない現場は事故の元です。資材置き場のラックがつくられていたり、道具類が大工毎にまとめられているかなど、気にかけて見てみると結構、現場のリアルな状況がわかるものです。
ただ、見学会用に会場すべてを整えて(道具や資材も一旦引き上げて)いると、普段の様子がわからないかもしれません。一方で、半日を見学会として残りの半日は作業に戻る、といった運営方法なら、普段の現場の様子と大差ない状況が確認できるでしょう。鈴木工務店は後者です。
建築中現場見学会を開催しているだけでは差別化にはならない

紀州山長の刻印が押された間柱。今回の住宅は外断熱で断熱等性能等級6ですが、外部に庇のつくサッシ上部には補強の断熱材を付加しています。
「結局どこも性能やつくり的にはあんまり違いがないんですよね」とは、見学会に参加してくださったお客様の感想です。工務店をいくつか見ていらっしゃる方で、他社さんの名前を聞くと工務店の勉強会などで一緒になるような真面目な会社の面々でしたので、「そりゃそうですよね…」と率直に思わされた次第です。
以前はハウスメーカー(HM)と工務店の比較検討が多く、見学会で木の梁や柱を見せる工務店は特徴を伝えやすかった(HMは基本的にボードとビニールクロスで隠してしまう仕上げのため)のですが、近年、建築中現場見学会に参加されるお客様は断熱等性能級6以上で実績を重ねている工務店同士で比較検討していることがほとんどです。そうなると、今回のお客様がおっしゃるように、施工法やメンテナンスに多少の違いはあれ、得られる性能そのものに大差はなく、お客様からしてみれば依頼先を選ぶ判断材料にはなりにくい、というわけです。

2階のアトリエ兼多目的ホールの壁は、間柱の間に棚をつくって壁面収納にする予定。外断熱により耐力壁をそのまま仕上げとして用います。
内装を含めた住宅の雰囲気を好きかどうかは、完成見学会に判断の場を譲るとして、建築中現場見学会では、最終的には材料・木の使い方と施工、プランの整合性など、設計力をどう伝えられるかが鍵になるのです。
柱や梁が見えるシンプルな木の住まいは、設計力で叶えられる
今回の住まいは、現しとなる柱や梁は紀州山長の杉無垢材を使用しています。見学会会場ではクッションキーパーで保護されていた部分です。また、2階は勾配天井で解放感があり、垂木が見えるている状況がそのまま仕上げとなります。

現しの柱や梁がクッションキーパー(黄色の保護剤)に保護されています。天井の垂木も見せる仕上げです。
そうした現しの柱や梁は、構造的にも間取り的にも整理されたプランによって機能美を見せてくれるもの。また、屋根面で断熱を十分に施すことにより、小屋裏空間まで快適な住まいとなり、勾配天井の下の空間もすべて生かせるわけです。
弊社では、「建物には美しいと感じる瞬間が3度ある」と言ったりしています。そのひとつ目が木の骨組みが立ち上がる「建方」です。詳しくはこちらのblogで解説していますのでぜひご覧ください。
→工務店のつぶやき。木造住宅の美しさを感じる瞬間。町田市の現場から | 株式会社 鈴木工務店
性能や建材そのものは数値やメーカーの仕様で確認しやすいのですよね。木の架構が見せるシンプルな機能美をについては、意識的に関心を向けてみると、つくり手による設計力やこだわりの方向性が見えてくるかもしれません。そこに共感できる何かが発見できれば、依頼先選びの有効な判断材料になりそうです。